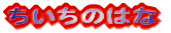
��J�h�̐����s�n�o�@�@�@�@���L�����ɖ߂�
���̑����@�����ɊW����m����^�ⓙ�@
|
| ���l�Ə�l |
|
�@�@�c�e�a�i1173�`1262)�́u���l�v�A�@�R�[����(1133�`1212)�́u��l�v�̎����g���܂��B���̑��A����ゲ�����S�āu��l�v�̎����g���܂��B���h�ɂ����Ă͏@�c�̂݁u���l�v�̎������āA�ǂݕ��͈ꏏ�ł����A�@�c�ȊO�́u��l�v�Ǝg�������Ă��܂��B�����܂ł͊F���ܓ��R�����m�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B�i�r�c�E���搶���悭������������������̂ŏ����}�l�Ă݂܂����j
�@���Ƃ��ƁA��y�@�ł́u��l�v�̎������g��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA��y�@�ɂ����Ă͖@�R���u��l�v�̎����g���݂����ł��B
�@���h�ȊO�Łu���l�v�Ǝg���͓̂��@�@������܂����A���@�@�ł́u���l�v�Ə̂����m�������l���܂��B�i�J�c���@�i1222�`1282)�͑吹�l�ƌĂԂƂ̂��Ƃł��B�j������ɂ���A�@�h�ɂ���Ă��̎g�����͂܂��܂��̂悤�ł����A�Ƃɂ������l�Ƃ���l�Ƃ������̂́A�m�̒��ł����̍����m�E�t���I�ȑ��݂̑m�ɗp�����鑸�̂ł���悤�ł��B
�@�^�@�ł͂Ȃ��@�c�̂݁u���l�v�̎������ĂĂ���̂ł��傤���B�܂��A�u���l�v�Ƃ������t���A�����납��A�ǂ̂悤�Ȑl�ɑ��Ďg����悤�ɂȂ��������肩�ł͂���܂���B�@
�@�Ƃ��낪�e�a�́A���m�a�]�̒��A����a�]�ɂ����āA��y�@�ł��g���邱�Ƃ̂Ȃ��u���l�v�ƕ\�L���Ă܂��B����͎��̐����ł����A�e�a�͖@�R��l�̂��Ƃ��A���ɑ��h����A���ʂȑ��݂Ƃ��Ă̎t���ł���Ƃ����Ӗ��������܂߂āu���l�v�Ƃ��������g���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�e�a���l�͎���u��Îߐe�a�v�Ɩ�����Ă����悤�ɁA�܂��̐l�X�i�e�a�̎q�����q�A���������l�X�j���e�a�̂��Ƃ������Ă�ł������Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�܂��A�w��`��x�i�o�@��l���j�̒��ł��@�R�̂��Ƃ��u���l�v�Ǝg���Ă���ӏ�������܂��B�w��`��x��ǂ�ł���Ɓw��t���l�̂��܂킭�x�Ƃ��w���M���l�A�������̂����܂Ӂx�A�w���ɂ����䂪�{�t���l�̌�O�Ɂx�ƁA�ǂ��炪�@�R�ŁA�ǂ��炪�e�a�̂��ƂȂ̂�������Â炢�ʂ͂���܂����A�o�@��l����݂�ƑP�M�i�e�a�j�́u���l�v�ł���A�P�M�[�i�e�a�j����@�R��l���݂�ƁA�@�R�́u���l�v�ł���Ƃ����\�}���ł��Ă���悤�ł��B
�@���Ȃ݂ɁA��ʓI�Ɂi�����ȊO�Łj�́u���l�v�́u��������v�Ɠǂ݂܂��B��J�g���b�N�ł��g���錾�t�ł��B
�@�������l�́u�͂���炵�傤�ɂ�v�ł͂Ȃ��A�u�͂����܂��Ɓv�Ɠǂ݂܂��B�@ |
|
|
|
|
| ���O�Ŏg���X�C�Ɛ����ɂ��� |
|
�@����Q�肷�鎞�Ƃ��A�X�C�̉��_���Ȃ�������A�_���Ă����������Ă��܂����Ƃ���܂��H���͂������h�������Ă܂����A�Ȃ��ꍇ�͍�����̂ł��B�����̂����������Ȃ��l�́A�X�C�ɏK�����Ȃǔ����a�����̂�Ŋ����Ă����ƂȂ��Ȃ������Ȃ��Ȃ�܂��B
�@������_���鎞�́A�����̏㉺�ɂƂ߂Ă��鎆���ǂ��炩�c���A�܂�Ȃ��悤�ɏ����P����܂��B����Ɛ����Ɛ����̊Ԃ��L�����C������̂ŋϓ��ɉ��_���₷���Ȃ�܂��B���̂܂܂ł͉��_���߂��Ă��܂��̂ŁA�����悻���_������˂����߂��A���Ɋ����Ă��鎆�͂��̂܂܂ŗ��Ă�Ƃ悢�ł��傤�B
|
|
|
|
|
| �V��Ƌ��� |
|
�e�a���l�i����3�N4��1��
�` �O��2�N
11��28���j
�@��J�h�ɂ����Đe�a���l�̌䖽����11��28���ł���܂��B����͋�������̂܂܌��݂̗�ɓ��Ă͂߂�11��28���Ƃ������Ƃł��傤���B��ʓI�ɂ����̓��ɂ��������Ƃ���Ă���l�q�ł���܂��B
�@�{�莛�h�i��������j�ł͋���11��28���z��Ƃ������̂ɉ��߂Đ�����̂ŁA�e�a���l�̌䖽����1��16���ƂȂ邻���ł��B
����3�N
4��
1���i���z��1173�N5��21���j
�O��2�N11��28���i���z��1262�N1��16���j
�@���ݓ��{�ň�ʂɎg���Ă����́A���ݐ��E�e���ł��g���Ă����@�ŃO���S���I��Ƃ������̂炵���̂ł����A����ȑO�Ɏg�p����Ă��������E�X��ɏC�������������z��̈��ł���Ƃ������Ƃł��B
�@�O���S���I���1582�N�Ɋ������A�C�^���A��X�y�C���ȂǂŎg����悤�ɂȂ�A���{�ɂ����Ă�1873�N�i����6�N1��1���j�ɓ�������邱�ƂɂȂ����Ƃ������Ƃł��B����Ė���6�N�ȑO�̗�((���A���z��(�A��j���ɓV�ۗ���w��))������Ƃ����A����ȍ~��V��((���z��i�O���S���I��j���w��))�Ƃ����Ă���A�Ƃ������Ƃł��B
�@�����E�X��ł�1�N��365.25���Ƃ���̂�1000�N��8���i1�N�ɖ�11.52���̌덷�j�̏C�����K�v�Ȃ̂ɑ��āA�O���S���I��ł͂P�N��365.2425���Ƃ���̂Ō덷��3000�N��1���ɂȂ����Ƃ����܂��B
�@�܂������E�X��ł�4�N��1��i4�Ŋ�����N�Ɂj�}������̂ɑ��āA�O���S���I��ł�400�N��97���[����}������v�Z�ɂȂ�炵���B�i�O���S���I��ł̉[�N�́A�@����N��4�Ŋ�����N�͉[�N�Ƃ���B
�A����N��4�Ŋ�����N�̂����A100�Ŋ�����N�͉[�N�Ƃ��Ȃ��B
�B����N��4�Ŋ����A100�ł�������N�̂����A400�Ŋ�����N�͉[�N�Ƃ���B�j
�@�ċG�I�����s�b�N�͂S�Ŋ�����N�ɊJ�Â���邻���ł����A�Q�O�O�O�N�i�[�N�E�V�h�j�[�I�����s�b�N�j�͖{���A��100�Ŋ�����N�Ȃ̂ʼn[�N�ɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł����B��100�ł�������N�̂����A400�Ŋ�����̂ʼn[�N�ɂȂ�Ƃ������Ƃ炵���ł��B
�@400�N��3��͉[�N�łȂ��N�ɉċG�I�����s�b�N���J�Â���邱�ƂɂȂ�܂����A���ꂪ���N�Ȃ̂��́A�����Œ��ׂāi�������e����Ă��Ȃ�������j�u�g���r�A�̐�v�ɂł����e���Ă��������B
�@�����ǂ�ł��悭������Ȃ��Ǝv���܂����A�����Ă���{�l���悭�������Ă��Ȃ��̂ł������炸�B�c�O�I�I
|
|
|
|
|
| �a�� |
|
�@��Ƃ́A���Ԃ̗����N�E���E�T�E���Ƃ������P�ʂɓ��Ă͂߂��̌n�̂��Ƃł��B���z��Ƃ������ꍇ�ł��l�X�ŁA�������ǂ̑��z��ɓ��Ă͂߂����͕�����܂��A5��21����e�a���l�̒a���Ƃ��A1��16����v�N�����Ƃ������͂܂��N���ɕ����Ă݂����Ǝv���܂��B�i���Ȃ݂ɍO��2�N11��28����
�����E�X��1263�N1��9���A�O���S���I���1262�N1��16���ƂȂ邻���ł��j
�@�a��̗��j���݂�ƁA863�N�܂ł͑埥��i��������ꂫ�A��������ꂫ�j�A���ꂩ��1683�N�̒勝��i���傤���傤�ꂫ�j�ɕς��܂Ő閾��i����݂傤�ꂫ�j���g���Ă������Ƃ��l����ƁA����3�N
4�� 1���E�O��2�N11��28���Ƃ������ɂ��͂Ƃ��ɐ閾��ɂ����ɂ��ł���ƍl�����܂��B
�@����������A���z��̗�@�ł��邻���ł����A���×�
����閾��܂ł͒�������`����ꂽ��@�ł���A���{�ŏ��߂č��ꂽ��@�͒勝��ȍ~�ł���܂��B����������܂芮�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����Ή����Ă����l�q���f���܂��B
�@���������炵�ď����Ă��܂����A���̂��Ƃ������Ă���{�l���S�R�������Ă��Ȃ��̂ł������炸�B�ؕ��I�I
����
�@����
690��-697 �@ ��������`����ꂽ��@
�@�V�P�� 692-�@ 764 �@ ��������`����ꂽ��@
�@�埥�� 764-
�@861�@�@��������`����ꂽ��@
�@�܋I�� 858- �@862�@�@��������`����ꂽ��@
�@�閾�� 863-
1683�@�@��������`����ꂽ��@
�@�勝�� 1684-1755 �@���{�ŏ��߂č��ꂽ��@
�@���� 1756-1798�@
���{�ō��ꂽ��@
�@������ 1798-1843�@ ���{�ō��ꂽ��@
�@�V�ۗ�
1844-1872(�����T�N�j���{�ō��ꂽ��@
�V��
�@�O���S���I�� 1873/1/1(�����U�N�j-���� |
|
|
|
|
| ���� |
|
�@����3�N�E�O��2�N�Ƃ����̂͌����Ƃ����N�̐������ŁA���݂͌����܂ł��Ȃ��u�����v�ł���܂����u�����v�܂ł�250�̌��������݂���Ƃ����܂��B�����̔N�̐����������Ƃ��Ă���悤�ł��B
�@���݂ł͓V�c�̍c�ʌp���̍ۂɉ��߂Ă��܂����A�����ȑO�͓V�ϒn�ق�Ύ��A�u�a�ȂǕs�g�Ȃ��Ƃ��N����x�ɉ��߂�ꂽ�Ƃ����܂��B���̂悤�Ȑ������͐^�@�I�łȂ��Ɣᔻ����邱�Ƃ�����A������g���悤�ɁA�ƌ����邱�Ƃ�����܂��B
�@1173�N�E1262�N�Ƃ����N�͐���Ő������N�ł����A����Ƃ̓C�G�X�E�L���X�g�̐��܂ꂽ�N�����N�Ƃ��Đ����A�L���X�g��Ƃ������Ă�����̂ł���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��l����Ƃ���͂���Ŗ�肪����悤�ł��B�������A���E�ōł��L���g���Ă���I�N�@�ł���A�����ł͔N���̐�������������Ƃ������Ă��A����Ő����邱�Ƃ������Ȃ����悤�Ɏv���܂��B
|
|
|
|
|
| �����ᔻ |
|
�@�����ᔻ�͂�������ǂ̌����n�߂�ꂽ���肩�ł͂Ȃ��悤�ł����A�쓇���ʎ��́u�{�莛��@����v��u����L�v����l����Ɂu�@�t���R�Ȗ{�莛����V�啪�̂���q���W�߂Đ����̎]�Q�����ꖔ���M�̖�k�ƕG�������Ĉ��S�̐��ۂ��������ꂽ�̂ɋN��������̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��Ă��܂��B
�@�쓇���ʎ��́u�����ᔻ�̗R���ƍ�@�v�ɂ��ƁA�u���������ᔻ�Ƃ������Ƃ͔��ɏd��ȍs���Ƃ��Ď戵���ċ���̂ŏ]���́u�Ă̂����v�̔q�ǂƓ��l�ɖ{�R���ɕʉ@�Ɍ���ꂽ�s���ł������ܒ���ȏ�̖@�v�Ɍ�����v���̂Ƃ���Ă��邻���ł��B�����āu�ᔻ�҂͈�ʂ̕z���g���I��Ȃ��œ��ɍu�t�Ƃ��k�u�Ƃ������u�҂̒����@��̓����ɂ���Đl�肳���v�Ƃ���܂����A���̕��������ꂽ�̂͏��a�R�O�N�ŁA�����A��@��ƌĂ�Ă�������̘_���ł���܂��B
|
|
|
|
|
| ��t�� |
|
�@�e�a���l�̂��Ƃ����^�i����j��t�Ƃ����܂����A����͖����V�c���瑡��ꂽ拍��i�������j�Ƃ���̍��������ł��B
�@���{�ɂ�����拍��Ƃ́A���삪�̑�ł������M�l�E�m���Ɏ���ł��瑡���鑸�������������ł��B�i���Ƃ͒����Ŏn�܂������̂ŁA���O�̈⓿��]�����邽�߂̏̍��ł������炵���j
�@�e�a���l�������ꂽ�������v�a�]�ɂ́u�R�Ƃ̓`���i�ł傤�j��t�́v�Ƃ���܂����A�V��@�E�Ő��̂��Ƃł���A�^���@�̋�C�i�O�@��t�j�ƂƂ��ɏ��߂ē��{��拍���ꂽ�̂����̓�l�������ł��B���{�ł͂܂��Q�T�l�������Ȃ��炵���̂ł����A���̒��ɂ͖@�R��l�i����E�~����t�j�@�@��l�i�d����t�j�������Ȃ�ׁA�e�a�E�Ő��E��C�ƂƂ��ɂP�W��t�̒��ɓ���Ƃ������Ƃł��B
�\����t
�@�@�`����t(�Ő�)�E���o��t(�~�m)�E�q�ؑ�t(�~��)�E
�@�@���d��t(�nj�)�E���ۑ�t(�^��)�E�����t(�V�C)�E
�@�@�O�@��t(��C)�E������t(���d)�E�@����t(�^��)�E
�@�@�{�o��t(�v�M)�E������t(����)�E������t(�o�f)�E
�@�@���֑�t(�r)�E���^��t(�e�a)�E�d����t(�@�@)�E
�@�@���z��t(����)�E�~����t(����)�E������t(�ǔE)
�@�܂��A�@�R��l�̉~����t�Ƃ���拍��͂P�U�X�V�N���R�V�c���瑡��ꂽ���̂ł����A�T�O�O���̂ɒ����V�c���瓌�Q(�Ƃ�����)��t�Ƃ���拍����Ă���T�O�N���ƂɂP�������A�P�X�P�P�N�V�O�O��ɂ͖����V�c��薾��(�߂����傤)��t���A�P�X�U�P�N�V�T�O��ɂ͏��a�V�c����a��(�킶���)��t�Ƃ���拍����i�v�V�j�����Ă���Ƃ����B
�@���Ȃ݂ɍ��m�a�]�Őe�a���l�͑�U�c���M�m�s�̂��Ƃ����M��t�ƌĂ�ł��܂����A�ʖ��A�b�S�m�s�A����m�s�ƁA��ʓI�ɂ͑m�s�ŌĂ�Ă��邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B拍��͑����Ă��Ȃ��悤�ŁA��ʓI�ɂ͌��M��t�Ƃ͌ĂԂ��Ƃ͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�e�a���l�͑��ɂ������̍��m�̂��Ƃ��t�ƌĂ�ł��܂��B��R�c�A���a�a�����u�{�t���a��t���v�Ɖr������A��S�c���^�T�t���u�{�t���^��t�́v���Ɖ]���Ă��܂��B��T�c�̑P���ɂ������Ắu�P����t�v�̍��̑��ɕ�����ł��Ȃ����炢�ł���܂��B�����v���ɐe�a���l�́A�����V�c���瑡����拍��ł͂Ȃ����A�^�@�̋����𖾂炩�ɂ������т��̂��A�̑�ȍ��m�Ƃ����Ӗ����������u��t�v�Ƃ����̍����g�����̂ł͂Ȃ����A�Ɛ������Ă��܂��B�i�����ő�t�Ƃ����̍������Ă��邩�͒m��Ȃ��̂ł����E�E�E�j
�@���^��t�Ƃ������O��拍��Ƃ����̍��ł��邱�ƁA����ɂ͖����V�c�Ƃ����ߔN�ɑ���ꂽ���O�ł���Ƃ������Ƃ��A�ŋߒm�����킽�����ł����B
�@���Ȃ݂ɁA������w�ɍ݊w���Ă������A�쐣�a�h�搶���u�e�a���l�̂��Ƃ��@�c���l�Ƃ����܂��B�@�c���l�Ƃ����܂��B�v�ƌ��������ς����Č����Ă������Ƃ��v���o���܂����B���̏@�c���l�Ƃ����Ăѕ��̒��ɂ͑�g���Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��ŁA�[�����h�̔O�����߂��Ă��邱�ƂȂ̂ł��傤�B
�@�����܂łɂ��ď����ĉ��ł����A���ݓ��h�ɂ����Đe�a���l�E�@�@��l�E�@�R��l�ɂ͑�t���͗p���Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���܂��B
�@�u��e���v�͈ȑO�u��t���v�ƌ����Ă��������ł����A���݁u��e���v�̖��̂����g�p���Ă��Ȃ��ƔF�����Ă���܂��B�i��������ł����́u��e���v�Ɩ��Â����Ă��܂����A�������Ƃ��Ă̎w�薼�̂́u��t���v�ƂȂ��Ă���̂Łu��t���v�̖��̂��g���Ă���悤�ł��B�j�u��e���v�u��t���v���@�h�Ȃǂł��g���閼�̂ł����A���������u��e���i��t���j�v�ƕ��p���Ďg���Ă���ꍇ�������悤�ł���܂��B
�@�����A�u���^�v�Ə����ꂽ�z�������̂ǂ����Ɍf���Ă���̂������l�͑����̂łȂ��ł��傤���B�u���^��t�v�Ə�����Ă��Ȃ��̂ŁA���܂��莋����Ă��Ȃ��ƕ��������Ƃ�����܂����A�i���̂悤�ɉ����m��Ȃ��l��������������܂��A�j�u��͂�A�O���ׂ��ł���v�ƌ������������Ȃ��Ă��Ă��邻���ł��B
�@�l�I�����͍T�������Ă��������܂����A�e�a���l���u���X��t�A���X��t�v�Ɓu�傢�Ȃ�t�v�Ƃ����Ӗ��ő��h�̔O�������Ďg���Ă������ƂƂ͂��Ȃ�Ӗ�����������Ă��Ă���̂͊ԈႢ����܂���B
|
|
|
|
|
| �����̓`�� |
|
�@�����i���傤���傤�j�ɂ́u�����`�v�Ƃ������̂�����悤�ŁA�Ȃ��Ȃ������Ă��������@����Ȃ��̂�����ł��B�Ⴆ�A��{�I�Ȃ��Ƃ͕ʂɂ��Ă��A���O�i�ǂ����イ�j�̕��ɒ����̂��Ƃ������Ă��炨���ƕ����Ă��u���̂��Ƃ͒�O�i���傤���イ�j�̕��A�������͓������Ȃǂɕ����ĉ������v�A�Ƃ����邭�炢���`�I�Ȃ��̂ŁA���̂��`������Ɏ���Ă�����̂������ł��B���O�̕���������`�����邱�Ƃ͂��܂�X�����Ȃ��悤�ȕ��͋C������̂ł����A�܂��R�c�N�Y�搶�����O�ł��������A��͂蒲���̂��Ƃɂ��ďڂ��������Ă������������͂��܂�L���ɂ���܂���ł����B�P�d�߂��A��N�̌�A��O�ɂȂ��܂������A��O�ɂȂ�ꂽ��ɂ͏ڂ����ׂ����Ƃ���܂Œ����̂��Ƃɂ��ċ����Ă����������悤�Ȃ��Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�����悻�A���w�̂��Ƃ͒�O�A�O�w�̂��Ƃ͓��O�ƌ��߂��Ă���悤�ł��B |
|
|
|
|
| �a�]�{�J���ɂ��� |
|
�@���w�̏o�d���Ă���l����̏�ɂ̂��Ă���a�]�{���J�����Ƃ��u�a�]�J���v�Ƃ����܂��B�����l�͐��M���I���A�O���̒����シ���ɊJ���܂����A���̑��̏��]��������l�͔O�����I�����ڂ̘a�]���n�܂�A�O��ڂ̒����܂ł��Ă���ƊJ�����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�i�l�I�ӌ��ł����j�P���ɍl���āA���̏��]�l�͂����̏ꏊ������܂Řa�]�{����{�I�ɂ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ő��̏��]�̐l���O���̒�����ɒ����l�ƈꏏ�Ɉ�ĂɊJ�������Ǝv���̂ł����E�E�E���w�ɏo�d����l�͐S�����Ƃ��Ĉ��ڂ̘a�]�͈ËL���Ă���̂�������O�Ȃ̂Ŏx��͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������Ƃ�����܂��B
�@��ʓI�ɂ͒����l����ɏ���������蓯���ɏ�������Ȃ��̂���{�ł���A�����T����̂��D�܂����Ƃ̂��Ƃ������ł��B����i�����炢�j�̎��A�����l���悸�������A��������ĊF������������A�����l���������������̂����ĊF�������������̂Ɠ������Ƃł��B
�@�������Ȃ���A�O��ڂ̒����܂ŊJ�{�ł��Ȃ��Ƃ����̂́A���܂藝�ɂ��Ȃ�����@�Ƃ͎v���Ȃ��Ɗ�����͎̂������ł��傤���H
|
|
|
|
|
| �䕶�̖��O |
|
�@�䕶�̖��O�́w���a�Ђ炪�ȔŁx�̖ڎ��ɂłĂ��܂����A�ȑO�͌䕶�̂͂��߂̌��t�����̂܂܁A�䕶�̖��O�ɂȂ��Ă����悤�ł��B�Ⴆ�A�꒟�ڂ̑�P�ʂł́u���l���킭�A�����̂�����́v�Ǝn�܂�܂��̂ŁA�䕶�̖��O���u���l���킭�v�ŁA��Q�ʖڂ́u�܂������̂����ނ��́v�Ƃ͂��܂�܂��̂ŁA�䕶�̖��O���u�܂������̂����ނ��́v�Ƃ������O�ɂȂ��Ă����悤�ł��B�䕶�̂͂��܂�́A�������̂��������߂ɂ��܂蕪����₷�����̂ł͂Ȃ������ł��傤���A���̕�����������䕶���o���������m��܂���B
�@���ꂩ��]���Ȃ��Ƃł����A�䕶�꒟�ڑ�T�ʂ̖��O�����a�Ђ炪�ȔŁx�ł́u�@���E�헬���ԁv�Ƃ���܂����A�䕶�̎n�܂��ǂނƁu�@���E�������ԁv�̌�肾�Ǝv���܂��B���݂̔��s����Ă���{�ł͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H
|
|
|
|
|
| �S���t�� |
|
�@���̓S���t�����܂��A��w���̎��A�F�B�ɗU���āh�ł����ςȂ��h�ɍs�������Ƃ�����܂��B���낢��Ȏ��������ĖႢ�܂������A�ǂ���s���Ƃ��܂���B�������Ƃ��Ε�����������Ȃ��Ȃ��ē����p�j�b�N��ԂɂȂ�܂��B���ǁA��肠�����u�K����芵���v�Ŏ����ōl���Ȃ���ł��ė��K���܂����B�ܘ_�A��U��̗��ł����B��U�肷��x�ɐl�̖ڂ��C�ɂ��Ȃ���p���������v����������v�������܂������A���x�����x���������K���邱�Ƃ�����ȂƎv���܂��B�v���Ԃ��A���������߂���������ȕ��������̂��Ȃ��Ǝv���o����܂��B
�@���ꂩ��A���U���ė��K�ɍs���܂������A�����Ƃ����C���X�g���N�^�[�ɏK���Ί�{���狳���Ă��炦��̂ł��傤���A�w���̍�����Ȃɂ������Ȃ����A�ܑ̖����v���������ł��̂Ŏ��͂ŗ��K���Ă��܂����B�F�B�ɋ����Ă��炤��������܂������A�ʔ����ł��˂��A�������������Ă�����Ă��l�ɂ���đS�R���t���Ⴄ��ł��˂��B���낢��l���đł��܂��������o��͂ގ��͏o���܂���ł����B�������A���̐l�͂����������Ɋ��o��͂Ȃ��A���̐l�͂����������Ƃ��ӎ����ď�B�����Ȃ��A�Ƃ������͂͂����芴���܂����B���̗F�B���������肵���w���҂ɏK�������͂Ȃ������悤�ł����A�l�ɋ����鎞�͂ǂ����Ă������̒͂��o�⎩���̈ӎ����Ă��鎖���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��Ȃ��Ɗ����܂��B���v���A�����Ƃ����w���҂ɏK���Ă���S���t���������̂��Ȃ��Ƃ͎v���܂����B��͂艽������b���厖�ł���Ǝv���܂��B
�@�ł����ςȂ��̗��K��ɍs���ƁA�l�X�ȃt�H�[���̑ł��������Ă���l�����邻���ł��B��肢�l�͂���Ȃ�Ɍ`���ł��Ă���̂ł��傤���A�����łȂ��l�͑łx�Ƀt�H�[��������Ă��܂������ł��B�����Ȃ�Ɉ����Ƃ�������ƈӎ����ăt�H�[�����ł߂�w�́E���K������̂ł��傤���A����l�H���A�u����ł́A�����t�H�[�����ł߂Ă���悤�Ȃ��̂��v�u�ςȕȂ����邽�߂ɂ킴�킴�Ԉ�������K�����Ă���l�������v�ƌ����Ă��܂����B
�@�S���t�����߂āA�悸�v�����Ƃ́A�����Ă��炤�l���u�߂������Ƃ������Ƃł��傤�B�S���t�́u�S�v�̎�������Ȃ��l�Ԃɕ��C�Ő��p����g������A��b���S���Ȃ��l�Ԃɓ���Z�p�����X�ƌ������A���܂��Ȃ낤�Ǝv���C�����������Ă��܂��܂��B�������A�����S���t�������邱�ƂɂȂ����炻���Ȃ��ł��傤���c�B��͂�A���ԓ��Ŋy�������̂��ǂ��ł��傤���A�����ł������X�R�A��L�������l�́A�v���̐l�ɋ����̂���Ԃł��傤�B
|
|
|
|
|
| �䓰�̑召�ƎQ�w�̑����Ƃ������� |
|
�@�䓰�̑召�ƎQ�w�̑����Ƃ������Ƃɂ��Ė@�v�̊i���ς�邩�ǂ����A�x�X�c�_�ɂȂ�܂��B
�@�䓰�̑召�ɂ��ẮA�e�X�̌䓰�ɂ����ĔN�ԍs���̖@�v�̌y�d�ɉ����Ċi�Ƃ������̂����݂�����̂ł��傤���A�n��n��ɂ����Ă��̓y�n�̊��K������܂��̂ŁA����͂���ő��d���Ă����͂Ȃ��ƍl���܂��B�������߂̎�ނɂ����āA�{�R�ł͐��M��́u�哑�v���ō��̂��߂ł���̂ɑ��āA�ʉ@�ł́u��v�̂��߂��ł���ʉ@����������A��ʎ��@�ł́u�^�l��ډ��v���ō��̂��߂ł������肷��悤�ɁA�䓰�召�ɊW�Ȃ������������Ƃ����݂���̂͊m���ł��B�O���]�̓��ɂ����Ă��������Ƃ�������ł��傤�B
�@�Q�w�̑����ɂ��Ă͂悭�������������Ƃ���ł����A�Q�w�̑����ɂ���āh�@�v�̊i�h���ς��Ƃ��Ƃ͂Ȃ��Ɗ�{�I�ɂ͍l���Ă��܂��B�����A�����̂悤�Ȑl�̂��킴�킵����ԂŁA�͂̂Ȃ��Ⴂ���A���������ł��߂��Ă��Ă��Q�w�l�ɂ͐����S���������Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���̂ŁA���̏o�����i���̍����A���̑傫���A���̗͋������j�͎Q�w�̑������l������K�v������ƍl���܂��B���̐��̏o�����Ƃ����̂��A�@�v�̊i�ɖ��ڂɊW���Ă��邱�ƂȂ̂ŁA�ӌ����������Ƃ���Ȃ̂ł��傤���A�Q�w�̑����炷��A�܊p���߂ɎQ�w���ɂ����̂ɂ��߂̐�����������������Ă��邩������Ȃ��ł͎c�O�Ȃ��Ƃł���܂����A���߂��鑤���炷��Ƃ����d�Ƃ��Ă̑��ʂƁA���M���l�M�̋����Ƃ������ʂ�����Ǝv���܂��̂ŁA�Q�w�����ĕ��i�ʂ�̂��߂���������ƌ����ƁA����͂���Ŗ�肪����ƍl���邩��ł���܂��B
�w�������x�ɂ́u���������V���v�Ƃ��āu���̊����ɐ����Đ��̍������͂���ׂ��B�L�����ɂĒႫ�͑R��ׂ��炸�B���̏��ɑ����̒��q���͂����ĉ����ӂ���@�Ƃ���Ȃ�v�Ƃ���܂��B���̍�������߂̊i�Ƃ������ƂɊW���Ă��邱�Ƃ���ł��傤���A�����ł́A�����܂ʼn����i���傤�j�̍���̘b�ł���Ɖ��߂������Ǝv���܂��B
�@�����A�i����j�̊ԍ�����A���߂̃X�s�[�h���ɒ[�ɕς��Ƃ������Ƃł͂���܂���B(����j�̉��͌y���ł��Ă��[�������܂ŕ���������̂ł��傤���A�Q�w�̑����ɂ͂��܂�e�����Ȃ����̂ł���Ǝv���܂��B���̂��߂̊i��ς��Ȃ����߂ɂ��A�{���̊i����Ђǂ��Ⴄ�i����j��ł��Ă��܂��Ă͂��ߑS�̂��Ⴄ���̂ɂȂ��Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B�P���ɍl���ċɘ_�������Ɓu���l��ډ��v�́i����j���u�^�l��ډ��v�́i����j�ɕ������Ă͂��������Ƃ������Ƃł��B�Q�w�̑������l�����Ă��A���܂�{���̊i�����E�����i����j��ł��Ƃ͋X�����Ȃ��ƍl���܂��B
|
|
|
|
|
| �L���̉��F |
|
�@���ʁA���L���̉��F�����t�ŕ\���Ƒ唼�̐l�́u�J�[���v�ƌ����ł��傤�B
�@���É��ʉ@�ŃL�����K�������́u�J�[���v�ł͂Ȃ��u�V���[���v�ƕ�������悤�ɑłĂƋ����܂����B
|
|
|
|
|
| �����ɂ��� |
|
�@�y����@�v�ł͉��ɁA�O�d�O���A����ɂ͕����i�����́j�����܂��B♁i���傤�j�E���Ái�Ђ��肫�j�E���J�i��イ�Ă��j�Ƃ����y��𐺖����̐��ɂ��킹�Đ����܂��B�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�y���������̐��ɕ����̂��A���������y�ɂ��킹�Đ��������̂��Ƃ������Ƃł��B�y�̕������ɕ����邩�畍���ȂƂ��������ƁA��͂�y�ɐ�����̂�������O�̂��Ƃ��ƈӌ���������܂��B
�@���̍l���́A�@�v���̂͐��������S�̂�����Ă����܂��̂Ŋy�����������̐��ɂ��킹�Ă����̂��{���̎p�E��{�ł���Ǝv���܂��B
�@�������A�Ⴆ�Ή��ɂōl���Ă݂�ƁA�O��ڂ̓��Ŋy�i�����j������ꍇ�A�y���͓��ڂ̉����Ƃ��āA�O��ڂ̒��O�ʼn����o���̂ŁA�����͐��������y�ɕ����邩�����ɂȂ�܂��B���i�������͏��̐������̐����ĉ������킹�Ă����܂����A���������������͊y�ɐ������킹�Ă����ƁA���������₷���Ȃ�Ǝv���܂��B
�@�ŋ߂ł́A�y���O�i�������j�̂Ȃ��Ɋy�m�̎��i�������Ă���l�������Ă��Ă��܂��B�ǂ��炪���킹��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���݂����@�v�̒m���������A���y�I�ɗD��Ă�����������Ă��Ă��܂��̂ŁA���Ɗy���s�b�^�����������f���炵���@�v�ɂȂ邱�Ƃ������Ȃ����悤�Ɏv���܂��B
�@���ÂƂ����y��͉��~�i������j�Ƃ����A���ɂň����悤�ɉ����܂邭�グ���艺������ł���y��ł��B���������Ӗ��ł͐������̂ǂ�Ȑ��i���j�ɂ��������Ƃ��ł���D�ꂽ�y��ł��B�������A�Ⴂ�����o�Ȃ��̂ŁA���߂̐����Ⴂ�ƂP�I�N�^�[�u���������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_������܂��B
�@���J�������i����������j�J���i�����グ��j�Ƃ����t�@�ʼn��𑀂邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�قڐ������̐��ɍ��킹�ĉ����������Ƃ��ł��܂��B
�@����ɑ���♂Ƃ����y��͍\���㌈�܂����������łȂ��y��ł��B�s�A�m�Ȃǂ̊y��Ɠ��l�Ɍ��܂����������ł܂��A�t�ɂ����Ή����͂���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�ʏ�Ȃ����t���鎞��♂̉����āA���ÁE�J�����̉��ɍ��킹�Ă����̂���{�ł��B
�@�����ɂ����Ċy�́A�������̓��ڂ̑S�̂��x�z�����{�ƂȂ鉹�i�{���j�������i�Ђ傤���傤�j�Ƃ������Ȃ�A�O��ڂ������Ƃ������ŕ����邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�����菭����̉��i���K����O�ꂽ���j�œ��ڂ��Ȃ肽���Ă���ꍇ�A������̉��A����i���傤���j�Ƃ������ŁA�J�E���Â͕����܂��B���̗��R�́A���ڂ̉����O��ڂ̉���������Ƃ��ߎ��̂ɂ��܂肪�Ȃ��Ȃ�_����Ƃ������ƂƁA♂����̂悤�ȊO�ꂽ���K���o�����Ƃ��o���Ȃ�����ł��B♂͂܂�����̉����o�Ȃ��̂ʼn����i�����ށj�Ƃ����A����ɂ���������̉��i�s���a���j�ŕ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���Â͑O�ɏq�ׂ��悤�ɁA���~���������Ĕ����ȉ��K���o�����Ƃ��ł��܂��B�������A���Â��y��ł�����A���������K�ɂȂ��O�ꂽ���Ő������Ƃ͂��Ȃ�n�����ꂽ�Z�p�E�������K�v�ł��B�O�ꂽ������ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�ꉹ�����鎞�́A�i�����j�ꉹ���������i�O�ꂽ�j�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��鎞�́A�O�ꂽ���i��j���������i�O�ꂽ�j�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ő�ςȍ�ƂɂȂ�܂��B
�@�J�̏ꍇ�ł��A���i���������K���o���悤�ɍ���Ă��܂��̂ŁA�O�ꂽ�����o���Ƃ������Ƃ́A����������胁�b�^���i�����������j��J�b�^���i��������j���o�������邱�Ƃ͍\���㖳���̂��邱�Ƃł���A�Z�p�I�ɂ����Ȃ������Ƃł���܂��B
�@���ɂ̕������A�Ⴆ�Ε����Ƃ������ŕ������Ƃ��܂��B�����������̐��͕ω����Ă��܂��B�X���Ƃ��Ă͉��������Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂����A�y���͂��������ꍇ�ł��o��������萺�����̐��ɍ��킹�Đ����č��킹�Ă���ɈႢ����܂���B�������A�������̏��Ɖ���Ő����o�������Ƃ�����ǂ��Ȃ�ł��傤�B
�@��{�I�ɂ͐������̏��̐��ɍ��킹��̂ł��傤���A�ꍇ�ɂ���Ă͒��a���ꂽ���S�n�悢���ɍ��킹�邱�Ƃ�����ł��傤�B�@�v�S�̂�ǂ����̂ɂ���ɂ́A���Ȃ�̉��y�I�Z���X�̂���Z�p�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ȏケ���̂��Ƃ܂��čl����ɁA���������K�̂ł�♂̉��ɍ��킹�����ÁE�J����������A���̉��ɐ����������킹�Ă����̂����z�ł���ƌ�����ł��傤�B
�@���ɂ̎O��ڂ��ŕ������ꍇ�A�l��ڍŌ�̉��͕����ŏI���܂��B�����A�y�Ɛ���������āA���ɂ̍Ō�ɁA�y�̉����C�����������ɕ��������ꍇ�A�y��̕������������K��ۂ��Ƃ��ł���͖̂��炩�ł���A�������̉����O��Ă������i�����������Ă����j�ƍl����̂��Ó��ł���ƍl���܂��B�������͉��ɂ�O�����ʼn���������₷���̂ŐS���Ă��߂�����K�v������ł��傤�B
|
|
|
|
|
| �S�����H |
|
�@�S�����H�B�u�ЂႭ�݂��傭�v�Ə����āu�ЂႭ�݂̂����v�Ɠǂ݂܂��B
�@�V��@�A���R�����ŗL���ȎO��@�ł͊ω���ՕS�����@�v(����̂������ЂႭ�݂��ق��悤)
�Ƃ����s�����s���Ă��܂��B
�@�w�Z�����x�܂��́w�ω��o�x�Ƃ������o�ɗR�����Ă���悤�ł��B�����܁i�ω����܁j�ɂ��������邱�Ƃ͑P�s�̌�����ςނ��ƂƉ�����A�������i�P�s�j�����čK�����肤�B�܂��A���̊��ӂ̔O������킵�A����ɂ����������Ղ̂悤�ł��B
�@�ޗnj��ɂ���k�R�_�Ђł́u�S���̌�H�i�����j�v�Ƃ�����_�a�i����j��������Ëg�Ձi���������j�Ƃ����Վ������邻���ł��B���̍Ղ�͑�E�������������̌�_���ɊW���Ă���Ƃ����܂�����s�v�c�ȋC�����܂��B
�@�o�����̃I�_�����i���@��j�̐_�a�Ƃ悭���Ă���Ƃ�����܂��B
�@�����ł́u�S�����H�v�A�u�S���̌�H�v�Ƃ��Đ_�Ђł��s����̂͂�͂�_���K���̉e���ł��傤���B
�@�^���@�̂��邨���ł́u����e���v�Ƃ����A�O�@��t�̖�����100��ނقǂ̂���������@�v������悤�ł��B
�@�S���Ƃ͎��ɏ������ʂ�S��ނ̐H�ו��i���j�������܂����A�K�������S��ނƂ����킯�ł͂Ȃ��\��ނ̈�Ƃ���������������悤�ł��B�w᱗��~�o�`�x�ɂ́u�S�Ɖ]���͑吔�ɂ��āA��߂Ĉ�S�ɔƂ݂�����v�Ƃ��邻���ł����A��͂�A�S���Ə�����Ă���ΕS��ނ̂��������������Ȃ�̂��S��Ȃ̂ł��傤���B
�@�w᱗��~�o�x���łĂ��܂������A�S�����H�ň�ԗL���Ȃ��o���w᱗��~�o�x�łȂ��ł��傤���B
�@�u᱗��~�v�Ƃ́A�T���X�N���b�g��́u�E�����o�i�v�t���ɒ݂����ꂵ�݂��Ӗ����A���߉ނ��܂̏\���q�̒��̈�l�u�_�ʑ��v�ƌĂ�Ă��鑸�ҖژA�̕���ł��B���̂��b�͒����Ȃ�܂��̂ł܂��ʂ̋@��ɂƎv���܂����A�S���ꂪ��S���ɗ����A�H�ׂ邱�Ƃ����ނ��Ƃ��ł����A�܂��ɋt���ɒ݂邳�ꂽ�悤�ȁA�Q�������ꂵ��ł����Ƃ���A���߉ނ��܂��u�m�����ɕS���̈��H�Ȃǂ��������Ȃ����v�ƌ����A����������Ƃ����e�͋~��ꂽ�Ƃ����܂��B
�@���{�ɂ����Ă��u�~�@�v�v�͒蒅���������s���ŁA�u�{��S�v�ƍ������ꂪ���ł������Ƃ��Ƃ͕ʂ̍s���ł���A�܂��u�S�����H�v���o�T���ʂɂ���A�Վ��Ƃ��ĕʂɍs����s���̂悤�ł��B
�@�w᱗��~�o�x�́u�S�����H�v�́u�����܁v�ł͂Ȃ��u�m�O�v�ɋ�����Ƃ���܂��B�w᱗��~�o�x�͒����ŏ����ꂽ���o�ƌ����Ă��܂����A�m���ɂƂ��Ă͓s���̂悢�����ɂ��݂��܂��B�^�@�̂��~�́A���̂悤�Ȃ������͂��܂��A�u���~�v���͓̂��{�l�ɒ蒅���������s���ł�����܂��B
�@�{��S�́w�~�������ɗ���o�i��������ɂ��傤�j�x�ɗR�����Ă���悤�ł����A�^�@�ł͍s���܂���B�܂��A���~������Ƃ����Đ���I�i�~�I�j�Ɉʔv�����u���A�֎q�ō��������ӉZ�̔n��������������悤�Ȃ��Ƃ͂��܂���B
�@�w᱗��~�o�x�ł́A�m���ɂ���������Ƃ���Ă��܂��B�������ɑm���Ƃ��Ă͂��肪�������Ƃł͂��邩������܂��A����������c�ɂ��������邱�Ƃɕω����Ă��܂��B
�@�S��ނƂ͌��킸�Ƃ���������̂�����������Ƃ������Ƃ́A�������͓I�Ȏ�����̂悤�Ɏʂ�A�^�@�ł͂��܂肻����Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�������Ȃ���A�������Ƃ����T�O�͕����Ƃ͐藣���Ȃ����̂ł���A�z�{�Ƃ����T�O�������ɂ͐Z�����Ă���͔̂ے�ł��܂���B
�@�^�@�ɂ����Ă��~�Ɂw᱗��~�o�x��ǂނ킯�ł͂���܂��A�w���M��x�̂��߂�᱗��~��Ƃ��ĂƂ߂܂��B�V��@��^���@�̂悤�ɕS�����H�̂悤�Ȃ�����������@�v������܂���B�o�T���Ⴄ�ƌ��������܂łł����A�u�S�����H�v�Ƃ������t�͐^�@�̌o�T�ł���w�������ʎ��o�x�ɂ��o�Ă��܂��B
�@�u����A���̕����y�ɂ������̉�������҂́A�c�i�����j�@�����H�i�����j����Ɨ~�i�����j�����́A����̔���i�͂��j�A���R�i���˂�j�ɑO�ɂ���B���E��E�ڗ��E�V���R�E����E�X��E���߁E�����i�݂傤���j�E�^��A�����̂��Ƃ��̂������̔��A�Ӂi������j�ɐ����Ď���B�S���̈��H�i�����j�A���R�i���˂�j�ɉm���i�悤�܂�j���B���̐H�i�����j����Ƃ����ǂ��A���ɐH����҂Ȃ��B�A�A�F�����A���i���j���ɁA�Ӂi������j�ɐH���Ȃ��ƈȁi�����j����B���R�ɖO���i�ق������j���B�g�S�_��ɂ��āA�����i�݂��Ⴍ�j����Ƃ���Ȃ��B���߂�Ή����ċ���B������܂������B���̕����y�͐�������ɂ��Ĕ������y�i�݂݂傤���炭�j�Ȃ�B���דD
�I���i�ނ��Ȃ�����j�̓��Ɏ��i�����j���B���̂������̐����E��F�E�V�E�l�A�q�d�����i�����݂傤�j�ɂ��āA�_�ʓ��B�i�����Ƃ����j����B���Ƃ��Ƃ���������ނɂ��āA�`�i�������j�ُ�Ȃ��B�A���]���Ɉ������邪�䂦�ɁA�V�E�l�̖�����B��e�[���i����݂傤���傤�j�ɂ��āA���ɒ����Ċ�L�i�����j�Ȃ�B�e�F�����i�悤�����݂݂傤�j�ɂ��āA�V�ɂ��炸�l�ɂ��炸�B�݂ȁA���R�����i���˂ށj�̐g�i����j�A���Ɂi�ނ����j�̑́i�����j������B�v
�@�H�ׂ悤�Ǝv������A�f���炵���킪��������Ƃ��Ȃ��łĂ��āA�S���i��������j�̈��H����������悤�Ɍ�����A�Ƃ����̂ł��B�������A�����H�ׂ�l�����Ȃ��āA����ɂ́A�F�����āA�����������ŁA������ŐH���Ȃ��Ė�������Ƃ����̂ł��B
�@��y�̓��Ƃ����܂����A�f���炵����\���������̂ł��傤���A�������ɂ͂������ė������Â炢���Ƃ�������܂���B���Ƃ��Ə�y�ɂ��܂ꂽ�l�͗~���Ȃ��A����~���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��傤�B�������̂��肳�܂ɍ��킹�Ă��̂悤�ȕ\���ɂȂ����̂ł��傤���B
���I���Ȃ��Ȃ�A�������Ă܂�������B�������̗��z�Ƃ����܂����A���̂悤�Ȑ��E����������Ă݂����Ǝv�킹�邨���Ƃł��B
�@�V�e��F�̏����ꂽ�w���ʎ��o�D�k��Ɋ萶��i��y�_�E�����_�j�x�̑�����p�������A�ɂ́A
�u���@�̖������y�i�������傤�j���A�T�O���i����܂��j��H�i�����j�Ƃ��v�Ƃ���܂��B
�@���߂̃e���|���ς��Ƃ���Ȃ̂Łu�萶��v�̂��߂����ꂽ���Ƃ�����l�͂����킩��ӏ��ł��B
�@�w�������ʎ��o�x�ł́A�u���߂�v�Ƃ���܂����A����́u���ɐH����҂Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�����킵�Ă��܂��B
�w��y�_�x�ł́u���y���@���@�T�O���אH�v�ƁA��y�ł̐H�ɂ��Ă���킵�Ă��܂��B
�����I�Ƃ����܂����A���̓I�Ȗ����ł͂Ȃ��A���_�I�Ȗ����A�S����������邷�������u���v�u�H�v�ɗႦ�Ă���̂ł��傤�B
|
|
|
|
��J�h�̐����s�n�o�@�@�@�@���L�����ɖ߂�
![]()