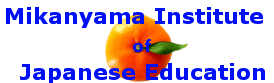
| 日本語教師養成講座の選び方 |
| 養成講座全体の流れは次のようなものです。 | |
| 1.座学で基本的な知識を勉強〜科目ごとにテスト | |
| 2.実践的な科目で模擬授業(15〜30分程度の授業を数回〜10回程度) | |
| 3.仕上げに実習(30分程度の授業を3回程度) |
| 養成講座は、大きく分けると以下の3つの受講システムがあります。 |
| 1 通学(クラスが固定している場合) | |
| こんなスタイル〜 | |
| 週に数回、決まった時間に通学。 決まったメンバーで受講〜実習 | |
| メリット | デメリット |
| 質問できる | |
| ライブで授業を受けられる | |
| 勉強仲間が作りやすい | |
| クラス全員の既習項目が同じなので、講師が折に触れ既習項目を話題に出せる。 既習項目を把握した講師が担当すると極めて有意義な授業になる。 |
|
| -∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- | |
| 2 通学(クラスが固定していない場合) | |
| こんなスタイル〜 | |
| 時間割から各科目を選択 (その科目については毎週同時刻に受講) | |
| メリット | デメリット |
| 質問できる | 勉強仲間が作りにくい |
| ライブで授業を受けられる | |
| 時間がある程度自由 | |
| 注意点:詰め込めば短期間で修了できる。 が、模擬授業などは準備に時間がかかるので、塩梅が必要。 |
|
| -∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- | |
| 3 オンライン | |
| こんなスタイル〜 | |
| 各科目を好きな時間に視聴 | |
| 科目修了試験を通学で受験(10科目程度) (講座によっては模擬授業のある実践科目は通学) (実習は基本的に通学) |
|
| メリット | デメリット |
| 通学のための移動があまりない | 質問できない |
| 座学に関しては時間が完全に自由 | ライブ感がない |
| 勉強仲間が作れない | |
| -∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- | |
| いい講座とは・・・ | |
|
講師の質 講座は10科目程度あります。講師は、ひとつ、または複数の科目を担当します。ほとんどすべての科目を担当する講師もいます。 シラバス(勉強の内容)は文化庁の指定があるのでだいたい同じです。 問題はそれを教える講師がどうなのか・・・。見学(視聴)させてもらうしかありません。 講座側の指定の時間、指定のビデオではなく、なるべくこちらの都合で選んで見学させてもらいましょう。講師にもピンキリありますので、講座側の都合で見せられるものは、その講座で最もウケのいいところになるはずです。そこだけ見てもあまり参考になりません。 また、専門的な内容を含みますから、見学しても授業の内容は理解できないかもしれません。が、講師の話し方や教室の雰囲気で、有意義な授業かどうかは判断がつくと思います。 「なにこれ・・・」「こんなものかなあ・・・」という感想を持ったら、その講座は避けたほうがいいでしょう。「あ、おもしろそう」と感じられる講師の講座を受けましょう。全員おもしろい、と感じられる講座はまずないでしょう。やむをえません。 全員つまらない、という講座はあると思います。 何がおもしろいかは人それぞれなので、自分なりの評価で決めましょう。 講座のキモになるのは「日本語教授法」と「文法」だと思います。 いい講師の授業は、ただ知識が羅列されるのではなく「なぜこの知識が必要なのか」「知識が日本語を教える上でどのように活用されるのか」はっきりわかります。残念ながら自分の教えている知識が、日本語の授業とどう関係するのかわかっていない講師も多くいます。 (講座により科目のタイトルはまちまちです。「文法」は「日本語教育文法」などの名前の場合もあります。「日本語教授法」は「初級の教え方」などの場合もあります。) いい講座でも、システムの都合上、見学ができないところもあります。説明会などに参加して判断するしかありません。このページを参考に、あらかじめ質問を用意しておき、説明者の誠意を判断してください。 検定試験合格率 検定試験合格率を高らかに掲げている講座もありますが、それは全受講生のものではなく、あくまで申告した人だけを計算した割合です。その養成講座を受講していても、受験していない人、受験しても講座に報告していない人の数は含んでいないはずです。合格率が気になる人は、どういった数字か尋ねてください。 特別に料金を取って対策講座を行っている養成校も多いです。それが本当の対策になっているか確認しましょう。市販の問題集や、オリジナルの問題を使っている講座は要注意です。対象の試験とまったく違うスタイルの問題での授業だとしたら、問題の分析も何もできていないということになります。 模擬授業の時間と方法 授業をうまくできるようになりたいなら、講師からのフィードバックを受けられる模擬授業を合計何分できるか、が重要です。 0分の講座もあれば、2時間以上になる講座もあります。 模擬授業を実施する科目のクラスの人数が多いと、ほとんどがグループワークで、講師からのFBが全く受けられないことがあります(クラスの選択が自由な講座では、選択したクラスによって人数が違う場合が多い)。 クラスが固定され、どのクラスも同じ人数で進行している場合は、どれだけの模擬授業を講師に見てもらえるか、はっきりしています。 実習は必ず講師が評価します。これも講座により回数、時間が少し違います。 | |
| -∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- | |
| 「将来何をしたいか」で選ぶ | |
|
養成講座に通う目的を下記のように大別して考えます。 1.日本語学校で働きたい 2.ボランティア教室で活躍したい 3.実習生などに教えたい 大学でも、養成講座でも、かつては「留学生」向けの授業だけを扱っていましたが、近年、文化庁の要請で、多くの講座が「生活者」「就労者」向けの授業方法を教え始めています。それぞれ1〜3の目的の対象です。 養成講座の中には、いまだ「留学生」向けの模擬授業・実習しかコースに組み込んでいないところがあります。目的が「1」であれば、そのような講座のほうが有利です。 あるいは「生活者」や「就労者」向け授業の勉強をカリキュラムに入れていても、それを教えている講師が、「留学生」しか経験がないということもよくあります。講師の努力でうまくいっている場合もあれば、留学生向けとほとんど同じ内容の場合もあります。「2」「3」が目的であれば、講師のキャリアを確認してもいいかもしれません。 | |
| HOME |
E-mail sinpe@mikanyama.onmicrosoft.com
Aich-ken Nagoya-si Mizuho-ku Mikanyama-chou
みかんやま日本語教育研究所