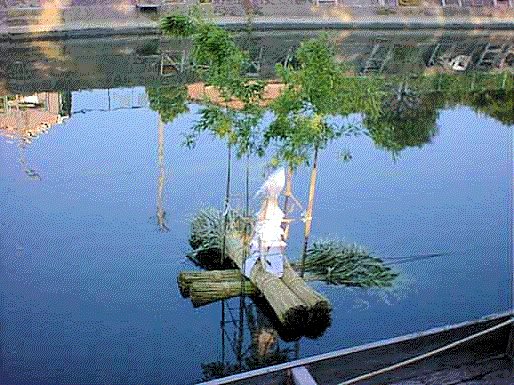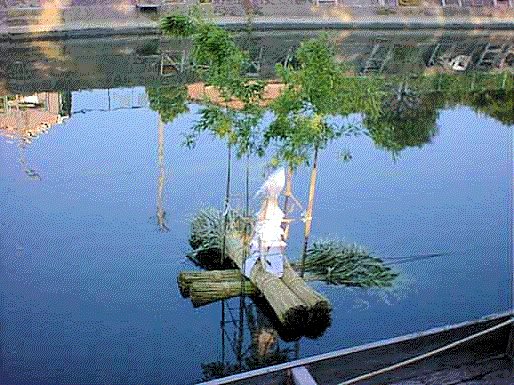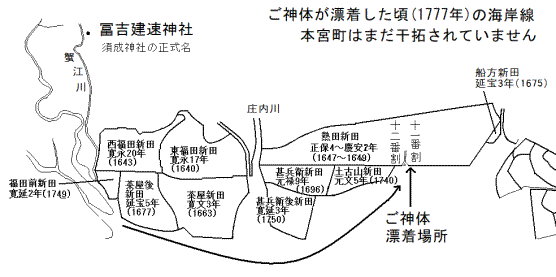須成祭における”御葭(みよし)ながし”神事において、蟹江川に流されていたご神体(写真)のことです。
ご神体は、刈り取った葭(よし)(葦(あし)ともいう)の束に災厄を封じ込めたものでして、毎年蟹江川に流されていました。
流れついたご神体は、その地域で75日間祀ったそうです。
安永6年(1777)六月(旧歴)に漂着したことが記録にあります。
御葭ながしは、疫病退散を祈願する天王(牛頭天王)信仰に由来する祭であり、蟹江川の河岸に繁茂するヨシ(葭・葦)を用いて神体をつくり、災厄をヨシに託して蟹江川に流していました。
その御葭が漂着した地域では御葭を丁重に祀りお祭りをしたそうです。
御葭ながしの行事は、津島天王社の牛頭天王にかかわる神事であり、津島神社関係したいくつかの神社で行われていました。
現在の須成祭では、ご神体は一旦川に浮かべますが、川に1週間浮かべたあと川に流すことはせず、70日間神社内で祀り、その後焼却しています。