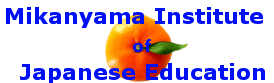
| 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ問題17「記述式問題」の書き方 |
|
試験Ⅲ問題17は「小論文」である。小論文には「書き方」がある。 書き方に従えば早く書ける。簡単に満点(20点)が取れる。あるいは、「~について書け」の「~」がわからなくても、「書き方」通りに書けば10点くらいは取れる。以下がその書き方。 その1.課題に忠実に 小論文の指示文には必ず「課題」がある。令和3年を例にとると、課題は以下。 課題1 知識伝達のためにどのような動画を用意するか具体的に提案する 課題2 上の動画を踏まえ、60分の授業でどのような活動を行うか具体的に提案する 課題3 上記は反転授業のメリットが十分に活用できるものである 課題4 400字程度で書く 課題5 活動が上級文法クラスで効果的と考えられる理由に言及する 前提として下記もある。 前提1 あなたは日本語教育機関の日本語教師である 前提2 上級文法クラスで来年から動画を用いた反転授業を行う 指示文の課題部分に下線を引く、丸をつける、書き出すなどして、課題を明確に意識できるようにする。 「小論文の書き方」についての本を何冊か見てもらえばわかるが、各種テストで解答として提出される小論文の多くは、課題の一部、あるいは全部を無視して書かれる。「そんな馬鹿な」と思われるかもしれないが、厳然たる事実。「そんな馬鹿な」と言いたくなるのは採点する側だが、あまりにも無視が多いので、たぶんいまさら気にしていない。粛々と低評価にするのみ。 『論文作法』(あるいは『薔薇の名前』)の作者として有名なイタリアの記号学者、ウンベルト・エーコは大学の卒論について「わたしは課題さえ満たしていれば最低でも半分の得点を与える」と述べている。検定試験の採点基準は謎だが「用語がなんにもわからなかったけど、課題通りに書いたら10点もらえた」という人はいる。 その2.メモを取る 課題を明確にしたら、何を書くべきかアイデアをメモする。小論文というのはアイデアが命。奇抜なアイデア、ということではない。あなたがその場で考えたことが大事。 出題者は「あなたは15分で何を考えることができますか」と問うている。(記述に使える時間はだいたい30分くらい。考える時間が15分で書く時間が15分と仮定した) だから、小論文の練習をするときも、短時間で行う必要がある。当日、15分で考えなければならないのに、1時間も2時間も熟考して考えをまとめていては練習にならない。まして、参考書を漁って「いい考え」を引っ張ってくるような真似をしては絶対にダメ。どんなに稚拙でもいいから、自分の頭の中から材料を探し、それを基に考えること。 令和3年であれば、まず「上級文法クラス」で何を学ぶのか具体的にイメージする必要がある。 担当したことがあれば特に問題ないが、なければ想像するしかない。 以下はあるグループで令和3年の記述にチャレンジしたときの記録。 初級向けの授業しかしていない段階だったし、数分程度の限られた時間というプレッシャーの中での考察だったのでやむを得ないが、ほとんどなにも思いつくことができなかった。実際の試験でもこのようなことは起きる。それなら、その思いついた範囲で書くよりほかはない。そして、書けるのである。 以下、そのグループが数分しかないプレッシャーの中でかろうじてできたメモである。メモの課題は河合が提示した。 メモ1 上級文法クラスで学ぶことは何か 課題1、2が「動画と授業の内容を具体的に書け」なので、まず授業で扱う項目を考える。 「~である」(これしか出なかった) メモ2 「~である」はどのようなところで使われる文法か これを考える理由も「メモ1」に同じ。 「小説において使用される」(これしか出なかった) メモ3 どのようなビデオを作るか 「メモ1、2」から具体的に考える。 「小説家が小説を書くビデオ」(これしか出なかった) メモ4 どのような教室活動を行うか 「メモ1、2」から具体的に考える。 (時間切れでグループでは考えなかった)(解答例参照) メモ5 なぜその活動が上級文法クラスで有効か 論理的整合性があれば後付けでかまわない。 (時間切れでグループでは考えなかった)(解答例参照) その3.メモの内容から、最も説得力のある組み合わせを選ぶ 日ごろからいい授業をしていていれば、いい内容のメモがたくさんできるはず。書きやすいもの、論理性があり、説得力がある課題5が書けるものを選ぶ。 「~である」しか思いつかなかったら、選びようがない。これで書く。「である」がほんとうに「上級文法」といえるか、ここで心配してもしょうがない。小論文の評価で最も重視されるのは、論理性である。「上級文法にはどんなものがあるかという知識」など、わざわざ小論文で測る必要はない。 その4.上記の組み合わせで、前提と課題を100%満たすか確認する 慎重に。 その5.構成する。だいたいは課題の順番通りに書いて問題はない 構成しつつ各課題に対するアンサーの字数が合計400くらいと判断できたら書きはじめる。 令和3年度 解答例 教授内容として「~である」を例に考える。 まず、動画として、小説家が小説やエッセイなどの文末表現を考えるシーンを設定する。動画には編集者などを登場させてもいい。文末表現を、書いた本人、または第三者が評価する内容で、学習者は「である」の持つニュアンスや、使いどころを理解する。教室活動においては、理解の確認として、「である」という文体がどのようなニュアンスを持っているか、抽象的に述べてもらう。その後、ふさわしい小説の一節などを各自が提示する。次に各自に作家、編集者、読者などの役割を与え、最近授業で扱ったテーマなどについて論述する。その際に、文末表現として「である」がふさわしいかどうか、各自の立場から意見を述べる。 上記のような知識伝達方法は教室では難しいが、動画では比較的容易である。そしてその内容及び教室活動は、日本語の小説や評論文などに触れる機会の増えている上級クラスの学習者にとって極めて実際的であり、効果が大きいと考える。(415字) 上記で紹介したグループでは「である」しか思いつかなかったが、ネイティブであれば日本語教育の経験の有無にかかわらず、上級の文法は必ず頭の中にあるはず。それを引っ張り出す必要がある。 どうやって引っ張り出すか。テキトーに難しいことを言ってみる。その中に入っていることがある。 さらに、検定試験の最中であれば、「難しい」日本語は目の前にある。問題文である。 令和3年度の、記述の問題文の中でいえば、「~において」「~を踏まえ」「~際」など。 内容について 上記回答例の内容は、下記のようなありがちな授業パターンを利用している。 導入 1.状況の中での例文提示 2.帰納的な意味、形の理解 3.演繹的な説明 4.理解の確認 練習 1.基本練習 2.コミュニカティブな練習 反転授業だからといって、大きく変える必要はない。導入の3は、一般的に教師主導だが、回答例では学習者主導に設定している。導入の2までが動画である。 こういった授業のパターンも、多くの参考書に書いてあることだが、それらを読んで具体的にイメージできるか、このパターンで授業をしてください、と言われて、実施できるか、が重要。それができるなら、このような小論文の課題にも利用できる。 もちろん日ごろの授業のアイデアも出やすい。小論文では、そういった教師であるか否かも測られている。 ちなみに、反転授業という言葉がまったくわからなくてもこの課題は100%書け、20点満点取れる。 動画で知識を伝達し、それを踏まえて教室活動をするのが反転授業なんだな、出題者はそういう意味合いで反転授業という言葉を使っているんだな、と理解して考えればいいだけ。 また、最近、いくつかの用語を並べて、そのうちのいくつかを選んで、「どのような意味で使っているかわかるように」組み込んで書け、という問題パターンが出ている。この場合、並んでいる用語は、必須用語なので、全部知っていてほしいのではあるけれど、不幸にして全部知らなかったらどうするか・・・。 自分で定義づけする。 定義づけしないで書けば、課題を無視したことになり、それはある意味「倫理的な違反」になる。 定義づけが一般の定義とずれているなら、それは「無知である」ということになる。 倫理に反する人間と、無知な人間と、どちらがより日本語教師にふさわしいだろうか。 悩ましい問題だが、人倫にもとるよりも、無知であったほうがより好いのではなかろうか。 そう思う。ゆえに、わからなかったら自分なりに定義づけして書くことをおすすめする。 以下、余談 上記も途中から余談のようなものだが・・・。 「そんなことよりも文法の授業そのものがイメージできないんですけど?」という人は、まだこの試験を受ける状況にはないということなので、ひと通り勉強してから受けたほうがいい。 問題は、養成講座などでひと通り勉強しているにもかかわらず、「文法の授業」「上級の文法」が思いつかない人。そもそも勉強のやり方がずれている。もちろん、(養成講座であれば)教えている側に大きな責任がある。 しかし、相手の責任ばかり責めていてもらちが明かないので、どこかで頭の使い方をトレーニングする必要がある。検定試験はそのトレーニングにちょうどいい。あくまで「調べずに解けば」であるが。 検定試験で問われていることの大半は、現実についてである。 現実の日本語、授業、コミュニケーション、頭の中で起こっていること、社会について、わかっていますか、と問うている。 様々な理論を机上の空論と思ったり、専門用語(概念)を参考書の上だけの知識と思わないこと。すべて現実につながっている。こういう意識で勉強し、問題を解こうとする。合格への早道であり、実際の教授活動においても、こういった意識は大きな助けになる。 最後に 過去問にも「解答例」があるし、調べればいろいろと解答例が出てくる。満点取れるか怪しい内容のものもあるが、いずれにしても、これらは時間をかけて書かれたもののはず。「こんなふうにちゃんと書かなきゃいけないんだ」と思わないように。 15分で考え、15分で書ける小論文など、内容的にたかが知れている。それなりに書けていれば問題ない。漢字のミスとか、構成のまずさとか、手書きで15分で書くのだから、あるのが当たり前。知識、考えが浅く見えるのも当たり前。課題を満たしていれば10点、内容が浅くても自分なりの考えが書かれていれば5点、合計15点は取れる。それくらいの気持ちで書く。 最後の最後に きれいごとに逃げない。令和3年の課題でいえば 「動画を作るに際しては、上級者への文法が効果的に使われ、その意味や使いどころが帰納的に理解できるものを作成する」 「授業においては、視聴された動画で得た知識を十二分に活用できる場としたい」 などと書いても意味がない。このような「きれいごと」は書く必要がない。「きれいごと」はだれでも書け、おおむね課題から外れるので、内容のない小論文の字数合わせとしか見られない。減点対象にはなっても、加点の対象にはならない。 自分の考えを書くのが小論文である。 日本語教員試験対策勉強会 |
| HOME |
E-mail sinpe@mikanyama.onmicrosoft.com
Aich-ken Nagoya-si Mizuho-ku Mikanyama-chou
080-4222-1336 (Kawai)
みかんやま日本語教育研究所