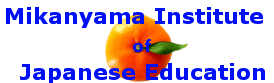
| 日本語教員試験(教育能力検定試験)に合格する |
|
過去問を解く 試験に強い人の勉強法がこれ。逆に熱心に勉強しても点が取れない人は、参考書をひたすら読むタイプ。 問題を解く=アウトプット。 それに対して、読む=インプット。インプットだけでは時間をかけても記憶に残りにくい。 現在の検定試験(日本語教員試験の内容は検定試験とほぼ同じ)は「考えて解く」問題にシフトしている。市販の検定対策問題の多くは知識重視の設問であったり、論理性を欠く問題もあるので、やらないほうがいい。なるべく新しい過去問を5冊程手に入れ解く。平成23年度から現在のスタイルになっている。 いつから過去問にかかるかと言えば、勉強を始めたらすぐにやるのがいちばん。 これも受験対策の常識。わからなくてもやって見ることが大切。なぜか・・・。 目標が見えるから。 勉強の総体が見えるし、各パートをどこまでの深度で学べばいいのか、感じられる。 わからないところがあっても調べない 1 本番では調べることはできない。勉強中もまず考える。知識がなくても論理性で解ける場合がある。 また、3分の1~4分の1程度の問題は「日本語の手続き的知識(記憶)」で解ける。日本語ネイティブであれば、日本語についての手続き的知識は100%持っていると言っていい。その「手続き的知識」をいかに「宣言的知識」にするかが勝負の分かれ目で、この能力は実際の教室でも求められる。 わからないところがあっても調べない 2 用語がわからないときは思い出す努力をする。特に「どこかで見た…」というレベルのものは問題文などから記憶を手繰り何とか思い出そうとする。脳内情報検索のトレーニングをする。 すぐに調べても忘れるので、七転八倒し、なんらかの結論を出してから調べる。忘れにくくなる。 選択肢の秘密~三一ルール 正解はひとつ。3つは不正解。用語がわからなくても選択肢が述べている内容で、グループ分けできる場合がある。明確にふたつのグループに分けられ、それが1:3であれば、1が正解。これを三一ルールという。(河合命名) 例:令和元年 試験Ⅲ 問題13 問4 1 こどもに歩み寄っているイメージ 2 周囲に歩み寄っていないイメージ 3 部下に歩み寄っているイメージ 4 クラスメートに歩み寄っているイメージ 「アコモデーション」ってなんか聞いたことがあるな・・・、というレベルで、ダイバージェンスの意味がはっきり思い出せなくても、イメージが違う2が選べる。 マークシートの試験の勉強というのは、問題文と選択肢を読んで、意味が推測できるレベルまででいい。 1:1:2でみっつのグループに分けられる場合なら、すくなくとも2のグループに入る選択肢は正解ではないことがわかる。 例:令和2年 試験Ⅰ 問題10 問4 1 ジョッキとビール。近くにあるもの。近接性。(「中身」から「包摂」と思わないこと) 2 花と桜。カテゴリーの上位と下位。包摂性。 3 紙(など)を破る→約束を破る。「ダメにする」という意味の拡張。 4 顔の耳(端)→パンの耳(端)。中心に対する端という意味の拡張。 3、4のようにわかりにくいものはメタファーと考えて外れは少ない。この場合2つあるので正解の選択肢ではない。当サイトの語呂合わせで覚えていれば楽勝で1を選べるが、そうでなくても2択までは持ち込める。 日本語教育能力検定試験 語呂合わせ集 日本語教育能力検定試験対策勉強会 「記述式問題」の書き方 ヒント集 |
| HOME |
E-mail sinpe@mikanyama.onmicrosoft.com
Aich-ken Nagoya-si Mizuho-ku Mikanyama-chou
080-4222-1336 (Kawai)
みかんやま日本語教育研究所